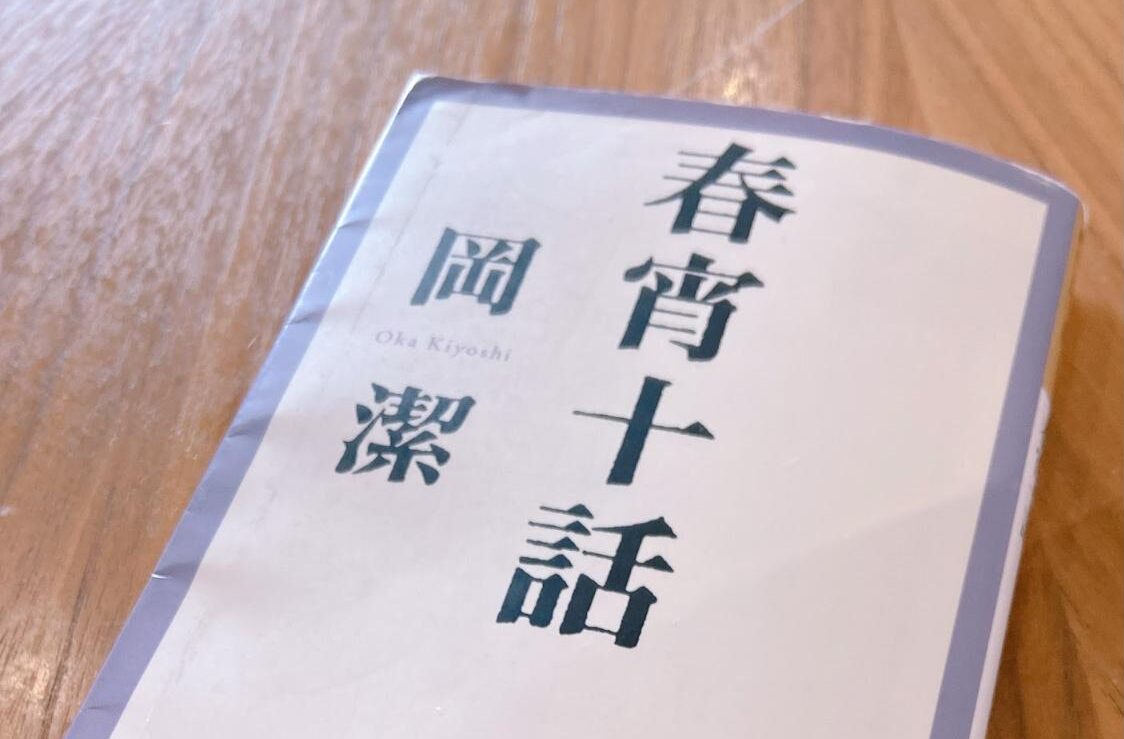こんにちは!講師の弓場汐莉です。
今日は、「近代日本が生んだ最高の数学者」と言われている岡潔(おか きよし)さんの著書から、
受験勉強の極意について学んでいきましょう!
最近わたしは、岡潔さんの『春宵十話(しゅんしょうじゅうわ)』という本を読んでいます。
この本のなかで、交感神経と副交感神経について書かれている部分があり、
それが非常に興味深いのです。

交感神経と副交感神経とは
はじめに基本的な知識として、交感神経とは、主にからだが興奮状態にあるときに働く神経です。
一方、副交感神経は、リラックスするときに働く神経です。
岡潔さんは、学問をするうえでも、これら二つの神経をバランスよく働かせることが重要であると述べていますので、
まずはその部分を一緒に読んでみましょう。

頭で学問をするものだという一般の観念に対して、私は本当は情緒が中心となっているといいたい。人には交感神経系統と副交換神経系統とあり、正常な状態では両方が平衡を保っているが、交感神経系統が主に働いているときは、数学の研究でいえばじわじわと少しずつある目標に詰め寄っているときで、気分からいうと内臓が板にはりつけられているみたいで、胃腸の動きはおさえられている。副交感神経が主に働いているときは調子に乗ってどんどん書き進むことができる。そのかわり、胃腸の動きが早すぎて下痢(げり)をする。━━中略━━本当は情緒の中心が実在し、それが身体全体の中心になっているのではないか。その場所はこめかみの奥の方で、大脳皮質から離れた頭のまん中にある。
(岡潔『春宵十話』より)
受験勉強における二つの神経の働き
これを受験勉強にたとえて考えてみましょう。

交感神経を使って勉強するとは、たとえば「今日中に英単語を100個覚えるぞ!」というように目標を定め、ひたすらノルマをこなそうとしている状態です。
このとき、からだは緊張し、集中力を高めています。
逆に、副交感神経が働くとは、一つの概念について理解を深めたり、
イメージを掴んだりするなかで、思わず「なるほど!」と声を上げたくなるような気づきや発見があるときと言えるのではないでしょうか。
リラックスした状態で、知的好奇心が満たされる感覚です。
バランスを崩すとどうなるか

では、どちらか一方の神経ばかりが働いてしまうと、どうなるのでしょうか。
交感神経に偏ってしまうと、ただ詰め込むだけの暗記になりがちで、
せっかく覚えてもすぐに忘れてしまいます。 常に緊張状態が続くため、
精神的にも疲弊しやすくなるでしょう。
一方、副交感神経だけに偏ると、「きちんと理解してからでないと覚えられない」という状態になってしまい、
なかなか暗記が進みません。
リラックスしすぎると、集中力が散漫になり、学習効率が低下することもあります。
理想的な勉強法:量と質を兼ね備える

どちらに偏っても、勉強はスムーズに進みません。
大切なのは、交感神経と副交感神経、両方のバランスを取りながら勉強を進めることです。
これにより、学習の「量」と「質」をともに高めることができます。
たとえば、時間を区切って集中的に暗記をおこなう(交感神経優位な)時間と、
学んだ内容をじっくりと振り返り、関連知識と結びつけながら理解を深める(副交感神経優位な)時間を、
意識的に設けるのがよいでしょう。
まとめ:緊張とリラックスの調和を

日常生活でも「緊張とリラックスのバランスが大切」とよく言われますが、勉強においてもまったく同じなのですね。
塾でも、「今日中に英単語500個を完ぺきに覚える!」と追い込むときもあれば、

お茶を配ったりウォーキングをしたりして、リラックスする時間を設けるなど、

意識的にバランスをとるようにはたらきかけています。
岡潔さんからもらったヒントをもとに、ぜひ受験勉強の質をいっそう高めていってくださいね。
それでは♪