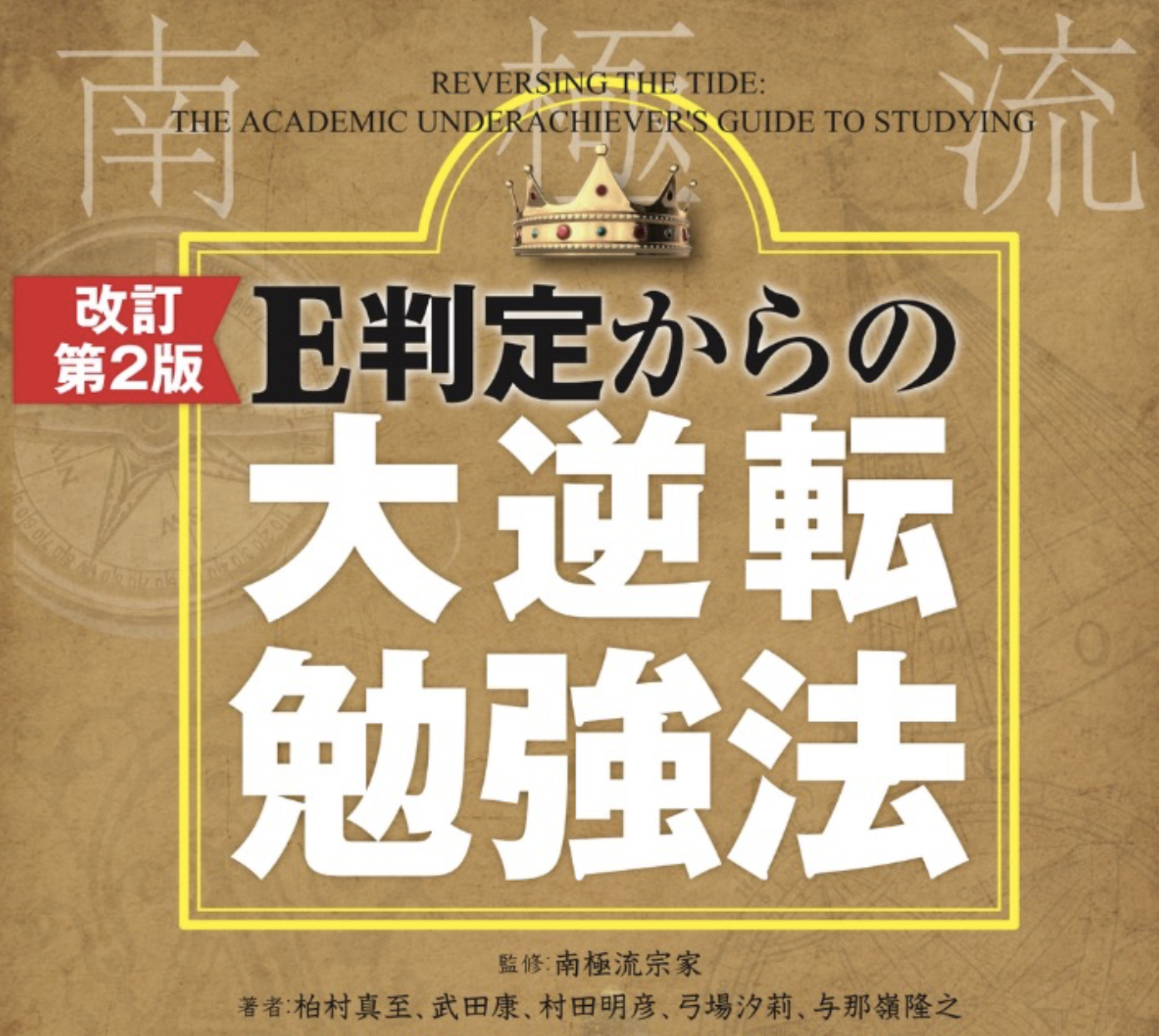大学受験で「国語力」は本当に必要?
こんにちは!
今回は、「大学受験における国語力の重要性」について、話していきたいと思います。
大学受験といえば、英語や数学、理科・社会といった教科に目がいきがちですが、
実はそれらすべての教科を支える土台となるのが「国語力」なんです。
一見、国語は文系の科目と思われがちですが、
理系の受験生にとっても実はとても大事な力。
今回は、「国語力ってそもそも何?」というところから、
「どうやって国語力を伸ばせばいいのか?」といった実践的なアドバイスまで、
この記事では、内容をわかりやすくまとめてご紹介します!
① そもそも国語力とは?なぜ大学受験に必要なのか?
まず、「国語力」って一体どんな力を指すのでしょうか?
よくあるイメージとしては、
「漢字を覚える力」や「古文単語を知っているかどうか」など、
テストで点を取るためのスキルと思われがちです。
しかし本当の国語力は、
言葉の理解力であり、
そしてそれを使って考える力です。
すべての教科のベースになる力
たとえば、数学の文章題。
問題文を読んで「何を聞かれているのか」「どんな条件があるのか」を正しく理解するには、
言葉の読み取り力が必要です。
英語の長文読解や理科・社会の資料問題でも、
「問われていること」を正しく読み取って、
そこから自分の考えを組み立てる力が求められます。
つまり、「国語力がある=読んで理解して、考えて答える力がある」ということ。
これは受験の全教科に共通して必要な“土台”となる力なんです。
賢い子ほど、国語力が高い?
たとえ数学が得意でも、文章題の意図を読み違えると正解にはたどり着けませんし、
英語だって単語の意味を知っているだけでは点が取れません。
だからこそ、「国語力を伸ばすことが受験勉強全体の底上げになる」という考え方は、
多くの指導経験を持つ先生たちに共通しています。
② 国語力がある人・ない人の違い
では、「国語力がある人」と「そうでない人」とでは、
一体どんな違いがあるのでしょうか?
国語力がある人は「何を聞かれているか」が分かる
まず大きな違いとして挙げられていたのが、
「問いを正確に読み取れるかどうか」という点。
たとえば記述問題で、
「このときの主人公の気持ちを、理由とともに説明しなさい」と聞かれたとします。
国語力がある子は、「気持ち」と「理由」の両方を求められていることをちゃんと理解して、
それに応じた答えを書けます。
でも、国語力が弱い子は、「気持ち」だけを書いて終わってしまったり、
逆に「理由」だけをつらつらと書いてしまったり。
つまり、“何をどう答えるべきか”の指示が読み取れていないことが多いです。
書かれていないことを想像で補ってしまう人も…
もう一つの違いは、根拠が曖昧なまま答えてしまうかどうかです。
「主人公は悲しかったって答えてるんだけど、その根拠はどこ?」と聞くと、
「だってかわいそうだから…」みたいな主観的な意見が返ってくることがあります。
国語力が高い人は、「本文に書いてあること」をベースにして考えるクセがついています。
一方、そうでない人は、
「なんとなくそんな気がする」「自分だったらこう感じるから」といった、
“本文の外”の情報に頼ってしまいがちなんです。
③ どうすれば国語力が身につくのか?
では、そんな大切な「国語力」をどうやって鍛えていけばいいのでしょうか?
まずは「問いを正しく読む練習」から
国語の問題を解くとき、多くの人がいきなり本文を読み始めてしまいがちですが、
実はその前にやるべきことがあります。
それが、設問をしっかり読むこと。
「何を聞かれているのか?」「何を答えるべきなのか?」を丁寧に把握することが、
正確な解答につながる第一歩なんです。
指導の際には生徒に、
「まず設問だけ読んで、どう答えればいいか整理してみよう」と声をかけています。
本文の根拠にあたる習慣をつける
もうひとつ大事なのは、「答えの根拠を本文から探すクセをつけること」。
例えば「どうしてそう思ったの?」と聞かれたとき、
「かわいそうだから」などの感情ではなく、
「〇行目にこう書かれていたから」と答えられるようになることが、
国語力を高めるポイントです。
この練習を通じて、
「感覚ではなく、根拠をもって読む」という姿勢が育っていきます。
国語ができると、すべての科目が変わる!
そしてなにより、国語力が身につくと他の教科の成績にも良い影響が出てきます。
なぜなら、数学でも英語でも、問題の指示や条件を正しく読み取る力が求められるからです。
「この生徒、理科の点数が伸びたな」と思ったら、
実は国語の読解力が上がったからだった、
なんてことも珍しくないです。
おわりに:国語力は“受験の土台”
今回お伝えしたかったことは、
国語力は単なる一教科ではなく、すべての学びの「土台」だということです。
問題を正しく読み、相手の言葉を受け取り、自分の考えを伝える。
そんな力は、受験だけでなく、
これからの人生を生きていく上でも欠かせないものです。
ぜひ、日々の勉強の中で「国語力」を意識してみてください。
きっと、見える世界が少しずつ変わってくるはずです。